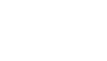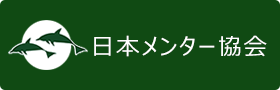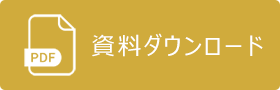「きく」・・というと皆さんはどちらの漢字を先に思い浮かべるでしょうか。
聞く
聴く
2つの「きく」の違いを問われるとなかなか普段意識していないこともあってか案外すぐに答えられないものです。
音や言葉などをきく場合、一般的には
「聞く」
の字を使うことが多いようですが、例えばラジオ番組や音楽、講義などをきく場合はどうでしょう。
こちらは「聴く」ですよね。
視聴や聴講、といった熟語からもそれがうかがえます。

あるいは、事情聴取となると、何やら込み入った話に耳を傾ける、といったイメージが湧くと思います。
『新聞用字用語集』※によると、きくは、「きく態度によって使い分ける」とあります。
とりわけ、「聴く」は「身を入れてきく」際に用いるそうです。
用語集の用例には、先ほどもあげたように「音楽を聴く」「講義を聴く」「事情を聴く」とありますが、その中で、
「声なき声を聴く」
という一文がありました。
特段、強調されて書かれていたわけではないのですが、とても印象的なフレーズに思えました。
では、「声なき声」とは?
様々思い浮かびますが、ひとつには相手の気持ちや感情に耳を傾けることではないか、と私は思いました。
実際にあったケースですが、マネージャーが「普段からメンバーの相談に乗って
コミュニケーションをとっているのに、匿名の職場アンケートでいつも不満が解消されていない!」
という悩みを抱えていました。
当のメンバーたちからすると、「マネージャーは全然わたしたちのことを理解してくれてない」
という声が口々に挙がっていました。
マネージャーからすると自分はしっかり話を「聞いた」のにと思っているようでしたが、
メンバー一人一人の発することばの事柄のみに焦点をあてて、そこに至るまでの気持ちや感情、
心の動きといった「声なき声」に耳を傾けて「聴いて」おらず、「こうすれば解決できる」
「どうしてこうしないのか」といった一方的なアドバイスや指導をしてしまっているようでした。
(これって、職場だけではなく、家族や友達同士でも見かけるケースですよね。)
はたして、わたしたちは普段のコミュニケーションにおいてどれほど相手の発することば
の話の内容や音声そのものだけでなく、「身を入れて」相手の気持ちを受け止めたり、
感情を理解しようとしたりしているでしょうか。わたし自身、だれかと会話を交わす中でも、
「声なき声」にも想いをはせて聴こうとしているかを、ふと考えさせられました。
音声情報のやりとりだけではなく、相手の気持ちや感情といった、表に表れない
「声なき声」を、身を入れて耳を傾けて聴くこと、すなわち「積極的傾聴」が、
お互いに気持ちを通じ合ったコミュニケーションをとる上で必要なのではないでしょうか。
~ 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 ~
※記者や校正者など新聞、通信、放送に関わる人が漢字表記の使い分などの標記の基準を定めたガイドブック。
今回は共同通信社『記者ハンドブック 新聞用字用語集』(第14版を参照した)
---------------------------------------------------
******************************************
研修マニュアル「Try!コミュニケーション」のご案内
****************************************
1テーマ30分で、「知り合う」~「信頼し合う」まで、
当マニュアルを使った「研修ファシリテーター認定講座」
※「ノムさんのコラム「Try!コミュニケーション」」は、
当マニュアルのワークのタイトルをコラムにし、毎月更新をしています!
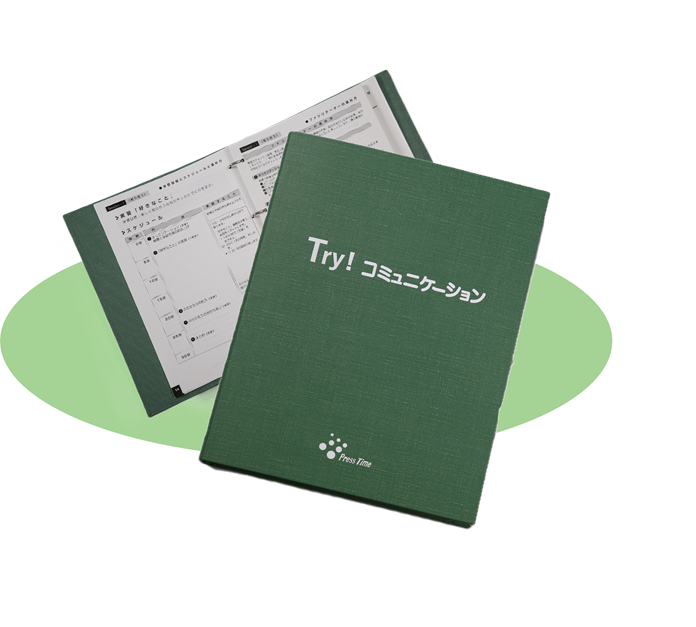
「Try!コミュニケーション」詳細はこちらから
「研修ファシリテーター認定講座」詳細はこちらから