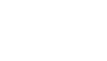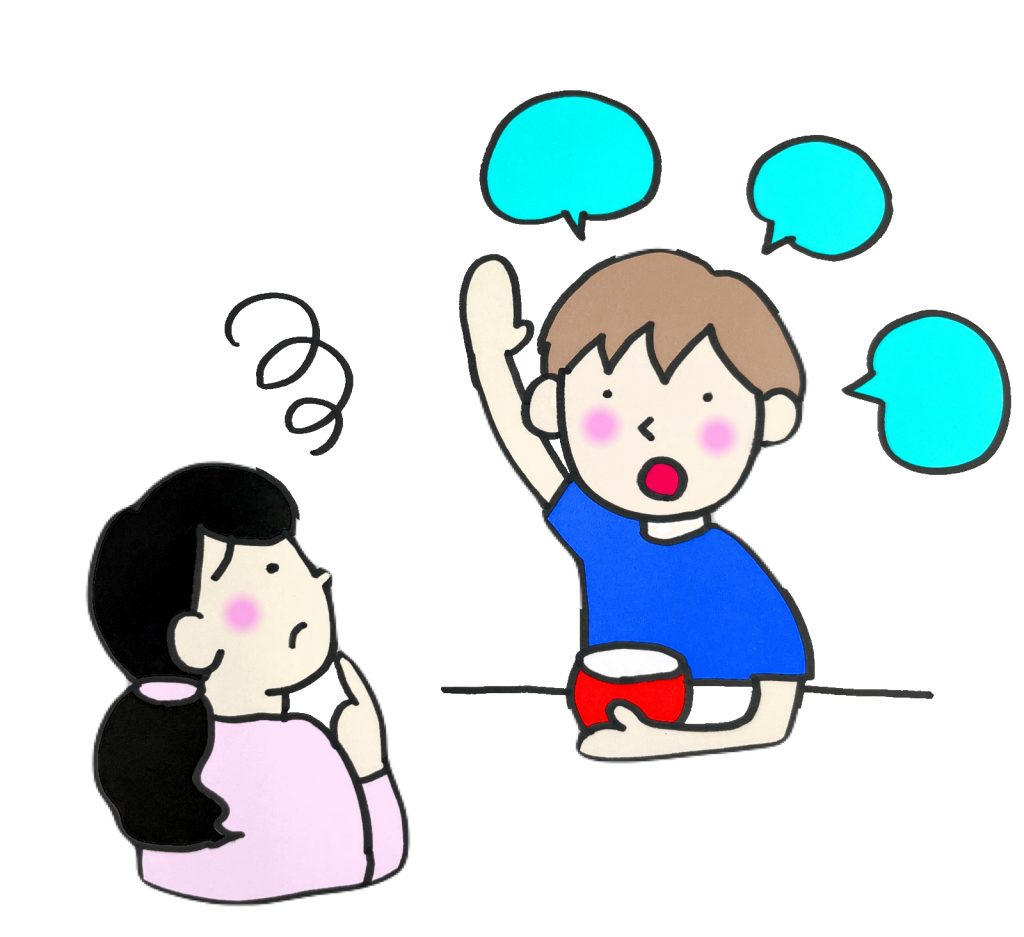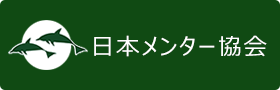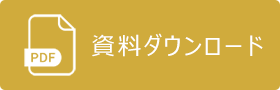ノムさんコラムでも紹介している「Try!コミュニケーション」
「どんな場面で使えるの?」 「活用法を教えて?」
「Try!コミュニケーション」とは30分のワークが12種類入っているマニュアル集です!
今回は活用場面を3つご紹介します。
***************************************************************
① 階層別コミュニケーション研修として
*****************************************

各ワークは学習項目もそれぞれ異なるので、
自社の課題に合わせて、自由に組み合わせて実施できます。
例えば・・
【積極性が足りない人が多い】
➡ ①”知り合う!”ワーク『好きなこと』で、まずは打ち解けてから
②”たずねる”ワーク『たずねる』で、更に信頼し合うキッカケについて学ぶ
【話を聞かない人が多い】
➡ ①”伝える”ワーク『富士山&ミニ流れ星』で一方通行から起こる様々な事柄に気づく
②”報告する”ワーク『二人の会話』で、「言葉のもっている意味」について学び、誤解のないコミュニケーションを意識する
【話し合い(合意)がうまくいかない】
➡ ①”みとめ合う”ワーク『私の買い方』で、一人ひとりの思いや価値観が違うことを分かり合う
②”合意する”ワーク『電車の中で』で、他人と通じ合う重要な要素は何かを学ぶ
【コミュニケーションの基本を学んでほしい】
➡ ①”はなす”ワーク『私の話し方』で、自分の話し方の特徴に気づく
②”きく”ワーク『聞くと聴く』で、2つの異なった聞き方を実践し、「聴くことの大切さ」を学ぶ
自己紹介し合うワークや、話し役や聞き役に分かれてのワーク、
皆で文章の解釈を考えるワークなど・・
ワークの種類が豊富なので、コミュニケーションについての様々な悩みに対応できます。
**********************************************************
② お互いを知り合うチームビルディングの場として
*********************************************************

全部で12種類のワークは全て、”相手と知り合える”ワークです。
お互いのことを知っていると、会話がしやすくなったり、
スムーズに仕事がしやすくなりますよね。
➡初対面同士なら、まずは”知り合う!”ワーク『好きなこと』で、楽しくお互いを知り合い、
”みる”ワーク『おや?』で、お互いの”ものの見方についてワイワイ話し合い、打ち解け合えると、
次の研修の良いウォーミングアップとなり、研修効果もあがります!
内定者や新入社員に限らず、部署やプロジェクト単位での実施もおすすめです。
1ワーク30分で実施できるので、使い勝手も抜群です。
**************************
③ 有志の勉強会として
**************************

コミュニケーションを様々な切り口で解説しています。
「話し方」「きき方」「障壁」「合意」など、テーマも豊富にあり、
「非言語」のワークで、言葉を使わないで相手の気持ちや感情に気づくコミュニケーション・ワークもあります。
コミュニケーションの理解を深めるにはうってつけです。
➡「各ワーク+解説(ワンポイント・レクチャー)付き」なので、頭だけの理解ではなく、
参加者全員が実感の伴った勉強会になるでしょう!
体系化されたマニュアルなので、安心して実施できます。
もし使い方に困ったら、私下舞に相談頂ければ解決します!
★TRYコミュニケーションはこちらから
https://presstime.co.jp/program/try_communication/