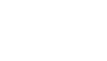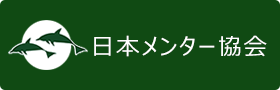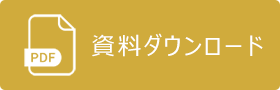とある家庭の食事風景です。
「お母さん、おはし!」
「お母さんはおはしじゃありません!」
このお母さんはわが子が食事にお箸が必要だけれども、手許にないので取ってきてほしい、
という意図で発言しているのはもちろんわかっているけれども、
相手に自分の必要としているものを頼むときに、きちんと具体的に伝えることが生活する
上で必要であるため、あえて
「お母さんはおはしじゃありません」
と返答しました。
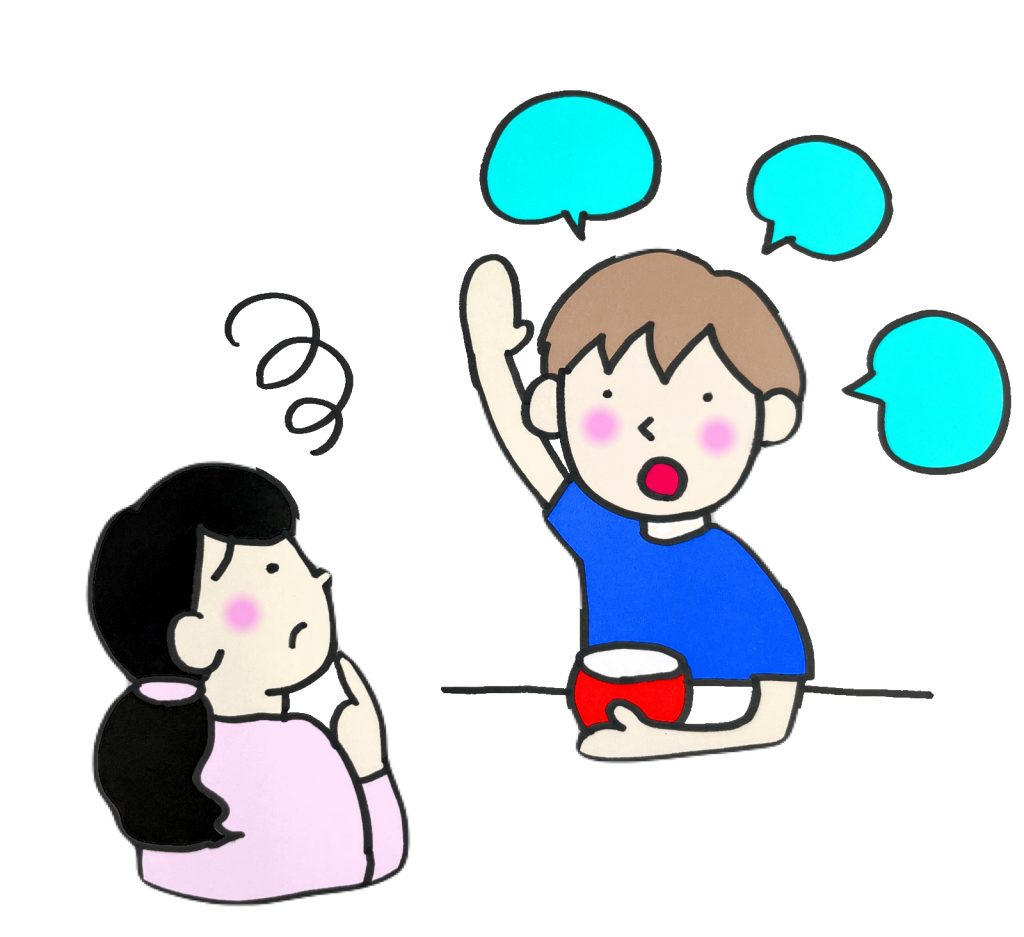
お察しの通り、私の家内と息子の会話ございます。
我が家に限らず、よくありがちな家族、親子の間でのやり取りだと思いますが、
コミュニケーション、とりわけ「伝える」という観点から非常に興味深いやり取り
であると感じました。
今回はちょっと長くなりますが、お付き合いいただけますと幸いです。
コミュニケーション、特に「伝える」ことについての話題に触れると、
「ハイコンテクスト」
「ローコンテクスト」
というワードを目にする方も多くいらっしゃると思います。
コンテクスト(英context)とは、辞書的な意味では、
1.(文章の)「前後関係」や「文脈」、「脈絡」、
2.(ある事柄の)「状況」、「環境」「背景」
ですが、
「ハイコンテクスト(high-context)」は
前提となる情報や知識、状況、背景、文化が共通認識としてあり、
暗黙の了解が多く行間を読むようなコミュニケーション
「ローコンテクスト(low-context)」は
共通認識がなくとも伝わるように明確に言葉で伝えるコミュニケーション
といったところでしょうか。
(蛇足ながら、上記は例えば「日本は空気を読むハイコンテクスト文化だ」とか、
「欧米をはじめとした諸外国はローコンテクスト文化だから言葉にしなきゃ伝わらない」と
いった、いささかステレオタイプな文化論として語られるケースも散見されますが、
それはまたの機会に。)
先ほどの、家庭内でのコミュニケーションはどうでしょうか。
かなり「ハイコンテクスト」なやり取りであるように見受けられます。
家庭内かつ親子間の食事中でのやり取りという、まさに「行間を読む」ことができ、
「暗黙の了解」が通じる状況です。
このような場合は、最低限の単語、あるいは言葉を発しなくても、
もしかすると「食事に必要なものがなくて食べられない」という表情や態度のみで
何となく伝わります。
しかしながら、生きていく上では常にそういった状況ばかりであるとは限りません。
むしろ、きちんと相手に具体的な言葉で伝えないと物事が進まない、「ローコンテクスト」
が必要な状況の方が多いのではないでしょうか。
おそらくは、「お母さんはお箸じゃありません」
の後に、お母さんは、
「『お箸がないので取ってください』でしょう。だれかに何かをお願いするときは、
ちゃんと何をしてほしいかちゃんと伝えようね」
とわが子に諭す、といった流れになると思われます(斯くいう我が家もそうでした)。
翻って、職場の中でのコミュニケーションではどうでしょうか。
日頃からお互い信頼関係があり、理解し合えているメンバー同士でしたら、
上記のような「ハイコンテクスト」で伝わりますが、顧客や協力会社など外部のひとと
仕事をする際、また社内であっても違うチームと仕事をする時は、そうはいきません。
「ローコンテクスト」、すなわち、共通認識がなくとも伝わるように明確に言葉で伝える
コミュニケーションが必要です。
こう書くと、どちらが優れたコミュニケーションかという話になりがちですが、
優劣や良し悪しはありません。
お互い気心知れたメンバー同士であれば、くどくど言うより「ハイコンテクスト」の方が
スピード感を持って伝わるでしょうし、違う立場の人たちの集まりであればしっかりと
伝わるように「ローコンテクスト」が必要になるでしょう。
コミュニケーション、とりわけ何かを「伝える」際には、自分と相手が置かれている
状況や、関係性をしっかりと認識したうえで「相手の立場に立って、理解できるように伝える」
ことがなによりも大切なのではないでしょうか。
~最後までお読みいただきありがとうございました~
******************************************
研修マニュアル「Try!コミュニケーション」のご案内
****************************************
1テーマ30分で、「知り合う」~「信頼し合う」まで、
当マニュアルを使った「研修ファシリテーター認定講座」
※「ノムさんのコラム「Try!コミュニケーション」」は、
当マニュアルのワークのタイトルをコラムにし、毎月更新をしています!
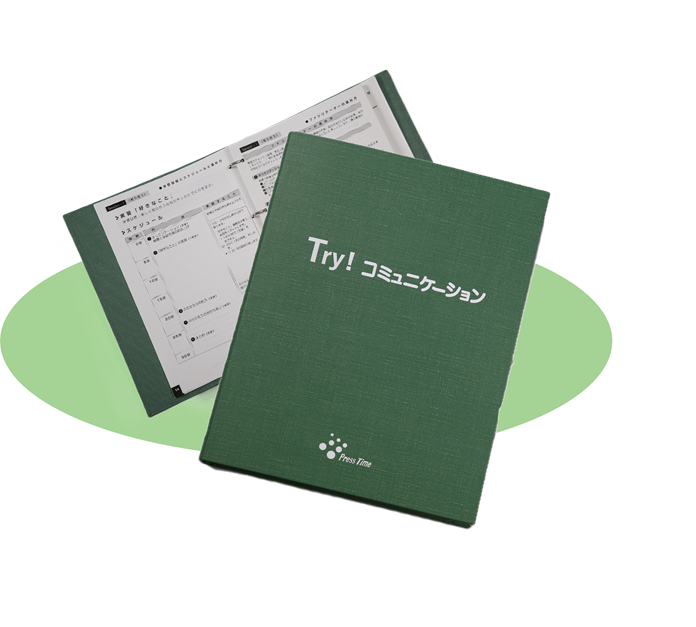
「Try!コミュニケーション」詳細はこちらから
「研修ファシリテーター認定講座」詳細はこちらから