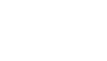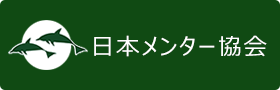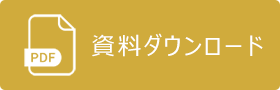私が本格的に研修ファシリテーターの活動を始めたころ、
師が私やファシリテーター仲間に「ねぇ○○さん、それは誰のため?」と尋ねる場面に度々出会いました。
ファシリテーターのトレーニングや研修終了後のファシリテーター間の振り返りの機会でのことが多かったと記憶しています。
尋ねられた者は(どうしてそんなことを聞くの?参加者のためなのに)などと戸惑いながら
「参加者(受講者)のためです」と答えていました。
師は困ったような、悲しいような、何とも言えない顔をされていました。
師にそういった顔をされると、私たちは自分自身と向き合わざるを得ませんでした。
師は「ファシリテーターは自分の枠組みにとらわれないで、
参加者の枠組みで『聴こう』『観よう』、そして『理解しよう』とする姿勢が求められている」と考えられていました。
また、そのためには「自分の枠組み(価値観、思い込みや固定観念、欲求、動機などで構成されている)を
よく理解しておくことが必要である」とも考えられていました。
研修での学習の主役は参加者であるという原則において、
ファシリテーターは参加者が学ぶことを支援、促進、援助する人であり、だからこそ介入をします。
その介入に影響が及ぼすものの一つが「枠組み」でしょうか。
どの「枠組み」で聴いているか、観ているか、それによって介入は変わることがあります。
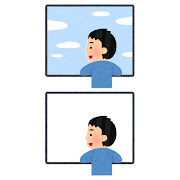
どの『枠組み』から観ているかで、
「観える景色」は変わります。
先の師の投げかけは、こういったことを直接的に教え、言い聞かせるのではなく、
私自身が探求し、学ぶ機会となっていたと感じています。
実際には容易いことではないですが、私はファシリテーターとして自分の枠組みにとらわれないで、
参加者の枠組みで『聴こう』『観よう』、そして『理解しよう』とする姿勢をいつも持っている者で在りたいし、
これからも精進してまいりたいと思います。
~最後までお読みいただき、ありがとうございました~
★今月のコラム担当・の代表 藤田の<代表メッセージ>こちらから!